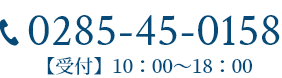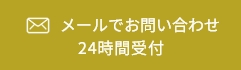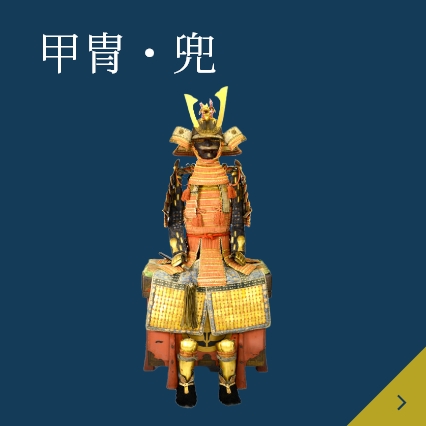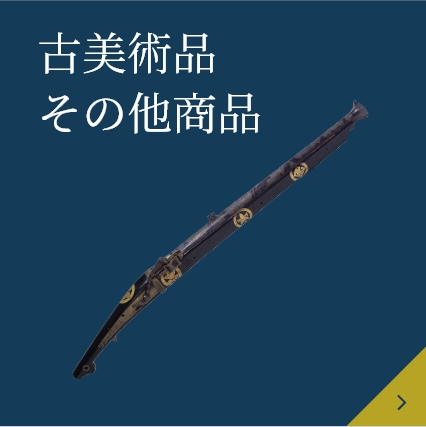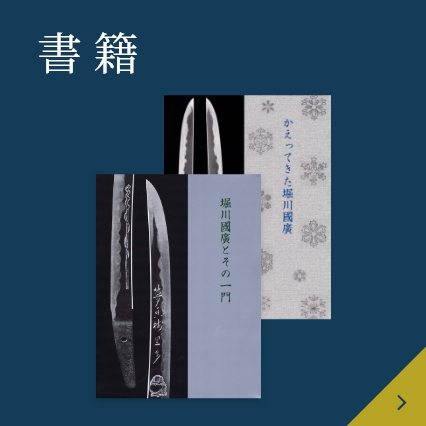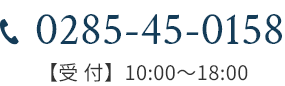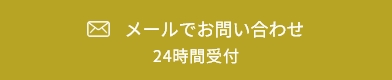ギャラリー
新撰組土方歳三の愛刀で有名
刀 和泉守藤原兼定
慶応三丁卯年八月日
Katana(Izumino-kami-kanesada-(Aizu11th))
| 商品番号 | NO.K00205 | 価格 | 参考品 |
|---|---|---|---|
| 登録証 | 北海道 | ||
| 鑑定書 | 特別保存刀剣 NBTHK Tokubetsu Hozon Paper (公財)日本美術刀剣保存協会 特別保存鑑定書 | ||
| 国 | 岩代国(福島県) | ||
| 時代 | 江戸時代末期 | ||
| 刃長 | 70.0cm (2尺3寸1分) | ||
| 反り | 1.5cm | ||
| 元幅 | 2.9cm | ||
| 先幅 | 2.0cm | ||
| 元重 | 0.7cm | ||
| 先重 | 0.6cm | ||
| 形状 | 鎬造、庵棟、身幅やや広く、反りつき、中鋒延びる。 | ||
| 鍛 | 柾目肌、地沸よくつく。 | ||
| 刃文 | 細直刃基調に小互の目交じえ、処々喰違刃となり、小沸つき、匂口やや深く明るい。 | ||
| 帽子 | 直ぐ小丸に先掃きかける。 | ||
| 茎 | 生ぶ、先剣形、鑢目大筋違、目釘孔一 | ||
| 附属品 | 金着二重ハバキ | ||
| 詳細説明 | 十一代兼定は天保8年12月13目、現在の会津若松市浄光寺町一番地に生まれ、幼名を友哉と称した。14才の時から父:十代兼定について鍛法を学ぶ。初銘を兼元と切り、十代兼定の代作代銘をなす。文久2年、会津藩主:松平容保公が京都守護職に任命されると、翌文久3年、幼名を清右衛門と改め、京都に上がり修業しつつ、和泉守を受領し、慶応元年に会津に帰る。受領後、刀銘は和泉守兼定と切る。新選組隊士の為に作刀したのはこの頃であり、副長:土方歳三の佩刀は慶応三年紀のもので、現在も東京日野市の生家に伝わっている。明治36年、67才にて没する。本作も慶応三年紀で柾目肌に細直刃を焼くなど保昌伝の出来を示し匂口明るい。 | ||

絞り込み検索
-
時代別一覧
古刀|新刀|新々刀|現代刀価格別一覧
~50万円|51万~100万円|101万~200万円|201万~300万円| 301万~400万円|401万~500万円|501万~1000万円|1001万円~ |要問合せ -
鑑定書別一覧
重要美術品|その他の鑑定書|鑑定書なし刀剣
特別重要|重要|特別保存|保存刀装具
特別重要|重要|特別保存|保存